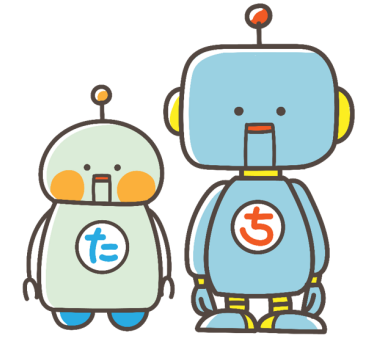次は、「条件分岐構造」のパターン3だよ!
分岐パターン3では、条件を追加していくらでも分岐を作ることができるんだ!

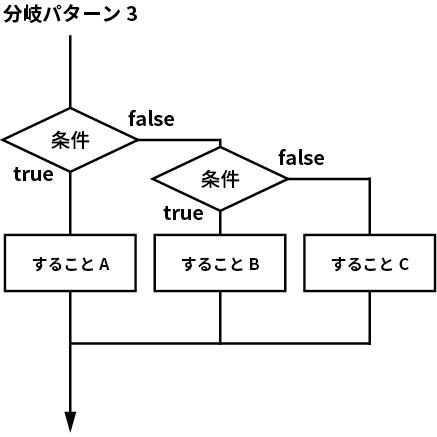

最初の条件を調べて、もし「True」だったら「することA」のプログラムを実行するけど、「False」のときには次の条件判定をするんだ。
そこでも「False」だったら、「することC」のプログラムを実行するよ!
「False」のときの次の条件は、いくつでも付け足すことができるんだよ!

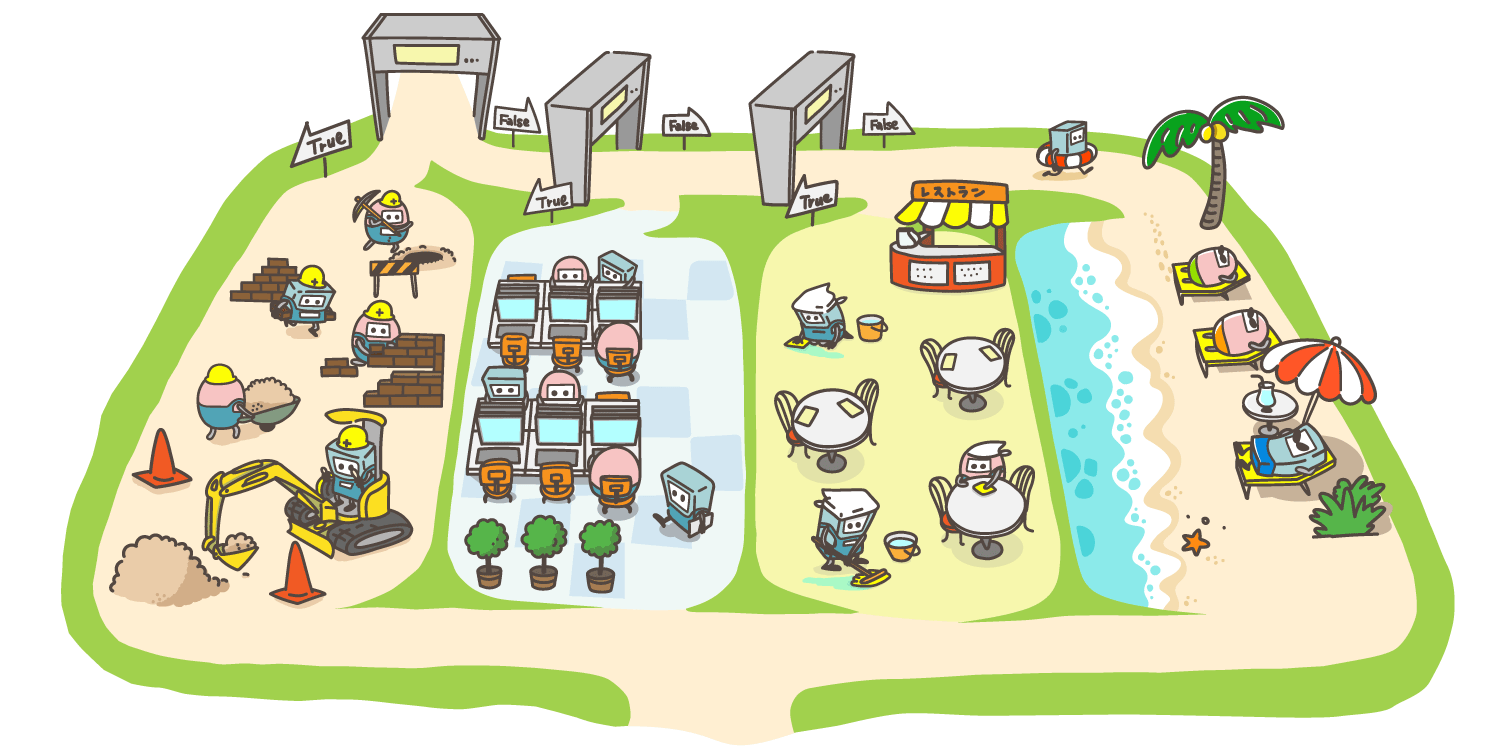
基本型
if elif else文
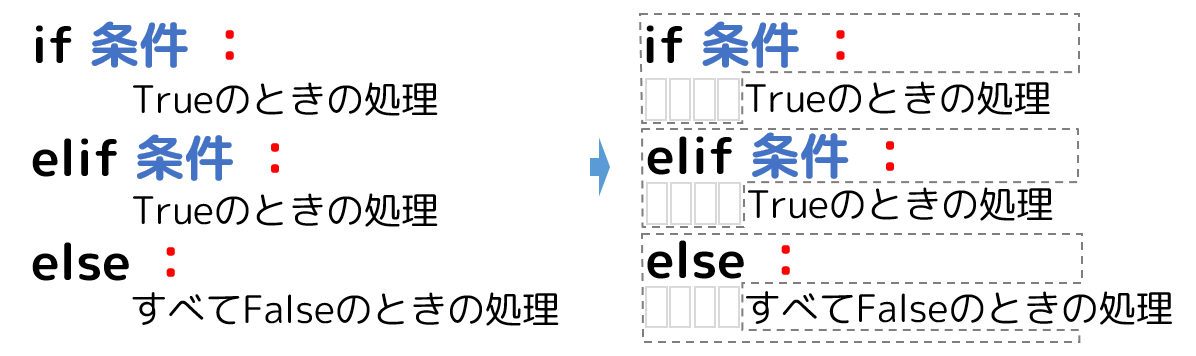

分岐パターン3は、「ifブロック」と「elseブロック」の間に「elifブロック」を挟んだ構成になっているよ!
「if elif文」とか「if elifブロック」っていうよ!


上から順に、条件に当てはまるか調べていって、当てはまったところの中の処理が実行されるんだ!
どれにも当てはまらなかったら、「elseブロック」の中の処理が実行されるよ!
何もする必要がないなら、「elseブロック」は省略しても大丈夫だよ!

使い方の例
📝1
硬貨を判別するプログラムです。
1.変数「coin」に、「1, 5, 10, 50, 100, 500」のいずれかの数値を代入します。
2.もし「coin」の値が「1と等しい」なら、「"1円硬貨です"」と出力します。
3.もし「coin」の値が「5と等しい」なら、「"5円硬貨です"」と出力します。
4.もし「coin」の値が「10と等しい」なら、「"10円硬貨です"」と出力します。
5.もし「coin」の値が「50と等しい」なら、「"50円硬貨です"」と出力します。
6.もし「coin」の値が「100と等しい」なら、「"100円硬貨です"」と出力します。
7.もし「coin」の値が「500と等しい」なら、「"500円硬貨です"」と出力します。
3.どれにも当てはまらないなら、「"偽物です"」と出力します。
coin = 100
if coin == 1:
print("1円硬貨です")
elif coin == 5:
print("5円硬貨です")
elif coin == 10:
print("10円硬貨です")
elif coin == 50:
print("50円硬貨です")
elif coin == 100:
print("100円硬貨です")
elif coin == 500:
print("500円硬貨です")
else:
print("偽物です")

「if elif elseブロック」を使えば、変数の値によって色々な処理を実行できるんだ!
これで、「if elif elseブロック」の使い方は、わかったかな?


変数「coin」の値を変えて、正しく条件分岐しているか確かめてみてね!
やってみよう
⌨️1
次のプログラムを、作成してください。
1.2つの変数「num_A」と「num_B」を用意し、それぞれに数値を代入してください。
2.もし「num_A」より「num_B」のほうが大きいなら、「num_Bのほうが大きい」と表示させてください。
3.もし「num_B」より「num_A」のほうが大きいなら、「num_Aのほうが大きい」と表示させてください。
4.もし「num_A」と「num_B」が等しいなら、「num_Aとnum_Bは等しい」と表示させてください。
📖 解答例と解説
num_A = 10
num_B = 20
if num_A < num_B:
print("num_Bのほうが大きい")
elif num_B < num_A:
print("num_Aのほうが大きい")
else:
print("num_Aとnum_Bは等しい")

「大きい」か「小さい」でもないなら、「等しい」ということになるよね!
「elseブロック」のところは、こんなふうにすることもできるね!

num_A = 10
num_B = 20
if num_A < num_B:
print("num_Bのほうが大きい")
elif num_B < num_A:
print("num_Aのほうが大きい")
elif num_A == num_B:
print("num_Aとnum_Bは等しい")
⌨️2
次のプログラムを、作成してください。
1.一つの変数に数値を代入してください。
2.もし変数の値が「2の倍数」なら、「2の倍数です。」と出力させてください。
3.もし変数の値が「3の倍数」なら、「3の倍数です。」と出力させてください。
4.もし変数の値が「5の倍数」なら、「5の倍数です。」と出力させてください。
5.もし変数の値が「どれでもない」なら、「どれでもない。」と出力させてください。
📖 解答例と解説
num = 111
if num % 2 == 0:
print("2の倍数です。")
elif num % 3 == 0:
print("3の倍数です。")
elif num % 5 == 0:
print("5の倍数です。")
else:
print("どれでもない。")

2の倍数というのは、「2で割った余りが0」ということだよね!
同じように、3の倍数も5の倍数も、「割ったときの余り」を調べると判断できるよね!


上から順に、条件に当てはまるか調べていって、当てはまったところの中の処理が実行されるんだよ!
例えば6のように、2の倍数でもあり3の倍数でもある場合は、「2の倍数です。」と出力されて終わるんだね。

- 分岐パターン3の基本型は、「ifブロック」と「elseブロック」の間に、「elifブロック」を挟んだ構成になっている 。
- 「elifブロック」は、いくつでも付け足すことができる。
- 「elseブロック」は、必要なければ省略できる。